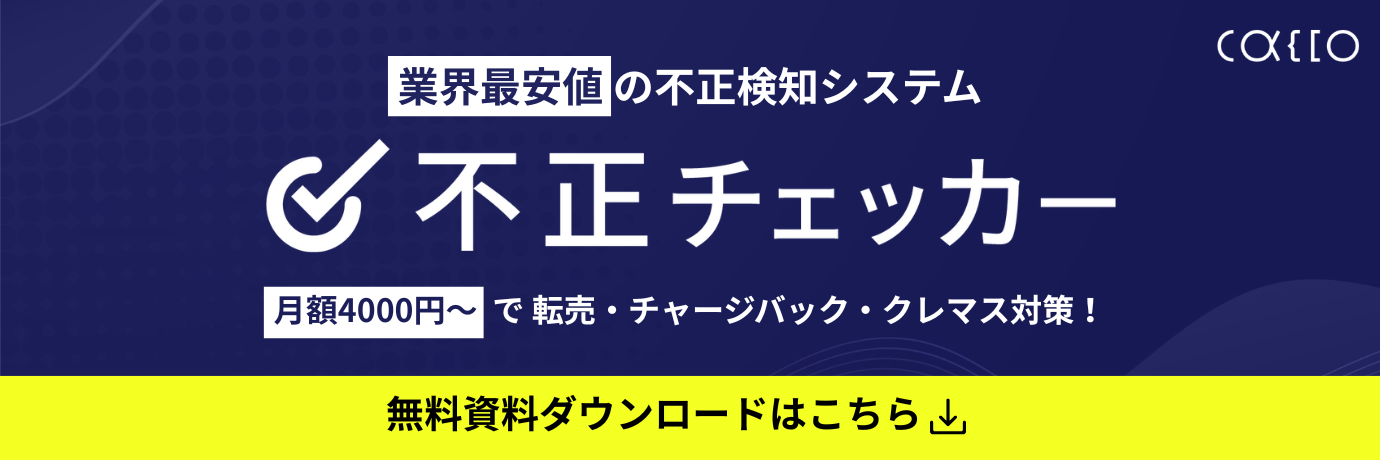「3Dセキュア認証に失敗したけど原因がわからない」
「エラーがでた時はどう対応すべき?」
このようなお悩みはありませんか?
3Dセキュア認証に失敗した時は、原因がなにかを明らかにして適切な対応をとることが大切です。
そこで本記事では、
- 3Dセキュアの認証失敗(エラー)時に考えられる主な4つの原因
- 認証に失敗した時の3つの対処法
などをお伝えします。
3Dセキュアの認証に失敗した時に、冷静に対処できるように本記事を一読して知識をつけておきましょう。
また、企業様は顧客情報を守るためにも、3Dセキュアと不正検知サービスを併用して重層的な対策をしていきましょう。
目次
3Dセキュアの認証失敗(エラー)時に考えられる主な4つの原因

3Dセキュアの認証失敗(エラー)時に考えられる主な原因は、次の4つです。
- 申し込み・設定ができていない
- カードが3Dセキュア認証に対応していない
- パスワードや個人情報などを誤入力している
- 不正使用の可能性があると判断された
それぞれ詳しく見ていきましょう。
【原因1】申し込み・設定ができていない
3Dセキュア認証(本人認証サービス)は、クレジットカード発行会社によって申し込みが必要な場合がほとんどです。
「申し込みや設定をしなくても、3Dセキュアによる本人認証がおこなわれる」と思い込んでいて、実は申し込めていないケースも少なくありません。
3Dセキュア認証に失敗した場合、申し込みできているかを確認してみてください。
また、「本人認証サービス」の申し込み・設定が済んだ後でも、クレジットカードの再発行や更新により再度申し込みが必要なケースがあります。
以下の記事では、3Dセキュアの登録方法をカード会社別に紹介していますので、本記事と併せて参考にしてください。
【原因2】カードが3Dセキュア認証に対応していない
クレジットカード発行会社やカードの種類によっては、そもそも3Dセキュア認証に対応していないことがあります。
その場合、カードの利用者側でできる対策はなにもありません。
もし本人認証サービス(3Dセキュア認証)を利用したいのであれば、対応しているクレジットカードに変更する必要があります。
【原因3】パスワードや個人情報などを誤入力している
3Dセキュアのエラー時によくある原因のひとつが、パスワードや個人情報の誤入力です。
何度も間違えてしまうと、不正使用を疑われてロックがかかってしまうこともあるので、再入力は落ち着いて行いましょう。
もしロックがかかると、パスワードの再設定やカード会社への問い合わせが必要になることもあるのでご注意ください。
また、「本人認証パスワード」を入力せずにキャンセルした場合、カードの本人認証に失敗してしまうことがあります。
正しく「本人認証パスワード」を入力して、カードの本人認証を完了させましょう。
【原因4】不正使用の可能性があると判断された
不正検知サービスの利用制限の対象になるなど、「不正使用の可能性がある」と判断された場合は3Dセキュアの認証に失敗することがあります。
たとえば、「本人名義以外のカードを使う」「一度に高額な支払いをする」などのケースです。
その場合、メールや電話で確認の連絡が入ったり、一定期間にわたって利用を停止させられたりすることがあります。
3Dセキュアの認証に失敗した時の3つの対処法

3Dセキュアの認証に失敗した場合、どのような行動を取るべきなのでしょうか。
本章では3つの対処法を紹介します。
- 申し込みや設定ができているか確認する
- ID・パスワードを再設定する
- クレジットカード発行会社へ問い合わせる
【対処法1】申し込みや設定ができているか確認する
パスワードが設定できていなかったり、個人情報に誤入力があったりすると、3Dセキュア認証が正しく実行されません。
カードが3Dセキュアに対応しているかチェックしたあと、申し込みや設定ができているかを改めて確認してみましょう。
また、カード会社によっては家族カードで本人認証サービス(3Dセキュア認証)を使う場合、カードごとに設定が必要なケースもあります。
今一度、本人認証サービスの申し込みや設定を見直してみましょう。
【対処法2】ID・パスワードを再設定する
クレジットカード会社によって異なりますが、一定回数以上誤ったID・パスワードを入力すると、セキュリティ上ロックがかかることがあります。
その場合、ID・パスワードを再設定してください。
多くの場合、公式サイト上に「ID・パスワードをお忘れの方」という注意書きがあるので、再登録してロック解除しましょう。
2回、多くても4回程度の失敗でカードにロックがかかるため、パスワードを誤入力しないように注意が必要です。
【対処法3】クレジットカード発行会社へ問い合わせる
対処法1・対処法2を試しても認証に失敗する場合や、認証に失敗する理由が分からない場合、クレジットカード発行会社へ問い合わせてみてください。
不正検知サービスによる、利用制限の対象になっている可能性もあります。
カード会社は不正利用防止対策を行っているため、利用するサイトや商品、金額などによっては、今まで利用できていたクレジットカードでも利用できないことがあります。
不正検知サービスによる利用制限の対象になっている場合、利用中のカード会社へ対応方法を問い合わせてみてください。
3Dセキュアだけに頼らない不正対策が求められる

3Dセキュアは、利用者の安全性を高めるために取り入れられている本人認証サービスです。
しかし、実は3Dセキュアだけでは十分な不正対策と言えません。
なぜなら、悪意のある第三者は、3Dセキュア認証を突破しようとさまざまな手口で不正行為を仕掛けてくるからです。
実際に、3Dセキュアの本人認証を突破されてしまった事例が過去にも報告されており、利用者には3Dセキュアだけに頼らない不正対策が求められます。
カードの不正利用を防ぐために利用者にできる対策の例は、次のとおりです。
【利用者にできる不正対策の例】
- 使用履歴や明細はこまめにチェックする
- IDやパスワードは分かりにくいものにして定期的に変更する
- ナンバーレスタイプのカードを利用する
- クレジットカードの裏には必ず署名をしておく
- SSL暗号化に対応しているサイトを利用する
クレジットカード番号が流出してしまった時の対処法や対策の詳細は、以下の記事を参考にしてください。
【企業向け】3Dセキュアと併せて不正注文検知システムの導入がおすすめ

前述したとおり、3Dセキュアだけでは十分な不正対策と言えません。
また、2025年3月末に3Dセキュアが導入義務化になりましたが、その影響から以前にも増して決済時におけるカード会社の審査が厳しくなっているのが現状です。
理由としては、3Dセキュアの導入率は上がっているが、カードの不正利用被害は依然として深刻な状況であるからです。
知らないうちに、カード会社の緊急措置によりクレジットカードの決済承認率が下げられてしまうと、原因不明の売上減少(売上の取りこぼし)やカゴ落ち増加など深刻な悩みを抱えることになります。
よって、巧妙化する不正手口から被害を防ぐため、3Dセキュアに頼りすぎない不正対策が求められます。
実際に、3Dセキュアと併せて不正注文検知システムを導入する企業が増えてきました。
▼不正注文検知システムとは
「属性行動分析」や「配送先情報」などをもとに、注文に不審な点がないかを複数の要素でリアルタイムに解析して不正を検知するサービス(※)
※かっこ株式会社「O-PLUX」での例
しかし、費用は安いものの検知精度の低いサービスを導入していることで、不正が防げていない企業も少なくありません。
「費用が安い不正注文検知システムを導入する理由」として、次のようなものが挙げられます。
- 使っているカートシステムで連携できるものがそれしかなかった
- 精度の高いサービスは開発費用が高額になってしまうため遠ざけてしまった
ただし、精度の低いサービスで不正が防げず、すり抜けが起こっているのなら、カートシステムをリプレイスするか開発費用をしっかりかけて高精度のサービスを導入したほうが、結果的にコスパが良くなります。
かっこ株式会社では、累計120,000サイト超えの共有データで高精度に不正注文を検知できる「O-PLUX」のトライアル利用を受付中です。
また、「O-PLUX」は不正対策と同時に、決済承認率が低下しているかどうかを可視化することもできます。
高精度なサービスを提供している「O-PLUX」について、詳しくは下記のバナーをクリックの上ご確認ください!
1万円で2週間のトライアル利用も受付中!
O-PLUXのトライアルはこちら
また、低コストでチャージバック、転売やクレジットマスター対策を行いたいなら「不正チェッカー」もおすすめです。
気になる企業様は、以下のバナーをクリックしてお問合せください。
\転売・チャージバック対策を業界最安値で/
不正チェッカーの資料DLはこちら
まとめ

3Dセキュアの認証に失敗した時も、原因と対処法を把握しておけば落ち着いて対応できます。
3Dセキュアの認証失敗(エラー)時に考えられる主な原因は、次の4つです。
- 申し込み・設定ができていない
- カードが3Dセキュア認証に対応していない
- パスワードや個人情報などを誤入力している
- 不正使用の可能性があると判断された
主な対処法としては、次の3つが挙げられます。
- 申し込みや設定ができているか確認する
- ID・パスワードを再設定する
- クレジットカード発行会社へ問い合わせる
なお、3Dセキュア認証だけではカード不正を完全に防ぎきれないため、利用者だけではなく企業も含めて対策することが重要です。
下記記事では、3Dセキュアと不正検知サービスとの違いを徹底解説していますので、不正対策を強化したい事業者様はぜひご参照ください。
\大手事業者の3Dセキュアと不正検知システムの併用事例あり/ 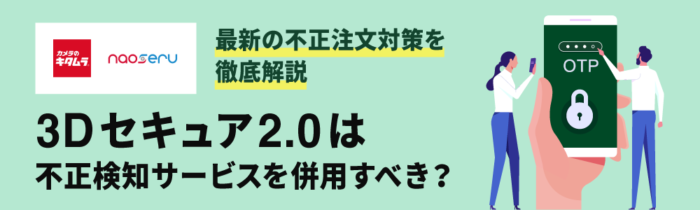 ※2022年10月より3Dセキュア2.0に移行となり、3Dセキュア1.0は提供が終了しています。
※2022年10月より3Dセキュア2.0に移行となり、3Dセキュア1.0は提供が終了しています。
3Dセキュア2.0についてはこの資料で解説しています。是非バナーをクリックし、ダウンロードください。






-8-1000x300.png)