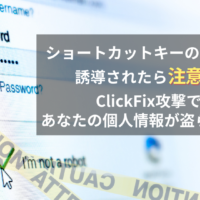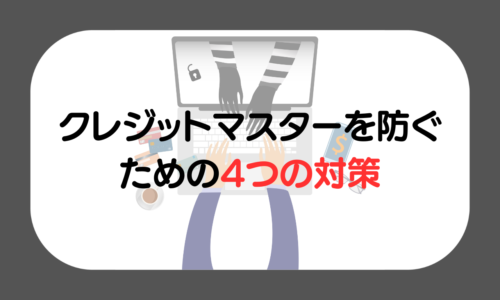通信サービス料金と合算で支払いができる「キャリア決済」。
3大キャリアを利用している契約者の方は、利用したこともあるのではないでしょうか?
この記事ではキャリア決済に関して
- メリットとデメリット
- 利用できるキャリア
- 決済できない場合に考えられる要素
などをご紹介します。
目次
キャリア決済とは商品代金を通信サービス料金と合算して決済できる仕組み

キャリア決済とは、商品代金を通信サービス料金と合算して支払いできる仕組みです。
- ソフトバンク(ソフトバンクまとめて支払い)
- ドコモ(ドコモ払い)
- au(auかんたん決済)
といった3大キャリアが提供しており、それぞれ名称が異なります。
このキャリア決済を利用する場合は、契約時に設定したIDとパスワードで認証を行います。
(一部、自動認証も対応しています)
利用できる加盟店はキャリア毎に異なります。詳しくはご自身が契約しているキャリアの公式サイトを確認しましょう。
契約者がキャリア決済を利用するメリット
このキャリア決済を利用するメリットは
- キャリア決済対象の契約をしていれば誰でも利用可能
- 決済方法が簡単
- 通信サービス料金と一緒に請求されるため複数の支払いをまとめられる
といった3点があげられます。
1.キャリア決済対象の契約をしていれば誰でも利用可能
1つ目のメリットは基本的にキャリア決済対象の契約をしていれば誰でも利用が可能という点です。
キャリア決済は、設定しているIDやパスワードの入力だけで利用できます。つまり、現金やクレジットカード情報は必要ありません。
そのため、クレジットカードを契約していない方や、インターネット上で情報の入力をするのを控えたいという方も利用できます。
(※フィーチャーフォンなどキャリア毎に一部非対応の機種もあります)
2.決済方法が簡単
2つ目のメリットは決済方法が簡単という点です。
キャリア決済は3桁もしくは4桁のパスワードの入力、もしくは自動認証で行います。
コンビニ支払いのように出かける必要もなく、非常に簡単です。
3.通信サービス料金と一緒に請求されるため複数の支払いをまとめられる
3つめのメリットは通信サービス料金と一緒に請求されるため複数の支払いをまとめられる点です。
キャリア決済で行った取引は、普段の通信サービス料金と合わせて請求されます。
複数の支払いがある方は、1つに合算されることで管理がしやすくなるでしょう。
契約者がキャリア決済を利用するデメリット
対してデメリットは、比較的少ない金額で上限額が設定されている点です。
キャリア決済にはご利用可能額(上限)が設定されており、超過した場合は取引ができなくなります。
キャリア決済のご利用可能額(上限)はクレジットカードと比較すると少ない金額のため、不便に感じる方もいるかもしれません。
しかし、ご利用可能額(上限)の設定は使いすぎの防止にも繋がるため、メリットと捉える方もいるでしょう。
また「少額の支払いを通信サービス料金と合算したいだけ」という方には問題ありません。
キャリア決済ができない場合に考えられる要素

余談ですが、すでにキャリア決済を利用している中には「なぜか決済ができなかった」という方もいるかもしれません。
キャリア決済ができなかった場合に考えられるのは
- ご利用可能額(上限)に達している
- ご利用制限をしている
- 通信サービス料金の支払いが期日までなかった
といったケースです。
1.ご利用可能額(上限)に達している
1つ目は前項でも触れたご利用可能額(上限)に達してしまっている場合です。
この場合は各キャリアの会員ページからご利用可能額を確認しましょう。契約内容によっては上限を引き上げられる可能性もあります。
2.ご利用制限をしている
2つ目はご利用制限をしている場合です。
初めて利用する方は初期契約時にキャリア決済のご利用制限をしているかもしれません。こちらも各キャリアの会員ページから確認しましょう。
3.通信サービス料金の支払いが期日までなかった
3点目は通信サービス料金の支払いが期日までなかった場合です。
通信サービス料金の支払いが滞ってしまうと、キャリア決済も利用できなくなります。まずは未払いの料金を支払いましょう。
これらの3点を確認しても利用できない場合は、契約しているキャリアまで問い合わせをしましょう。
キャリア決済を利用できるECサイトや月額制サービスも
今回は「キャリア決済」について詳しくまとめました。
当初は利用できる加盟店が少なかったキャリア決済ですが、ECサイトや月額制のサービスなど幅広く使えるようになってきています。
興味のある方はご自身が契約するキャリアの詳細ページを確認してみてください。