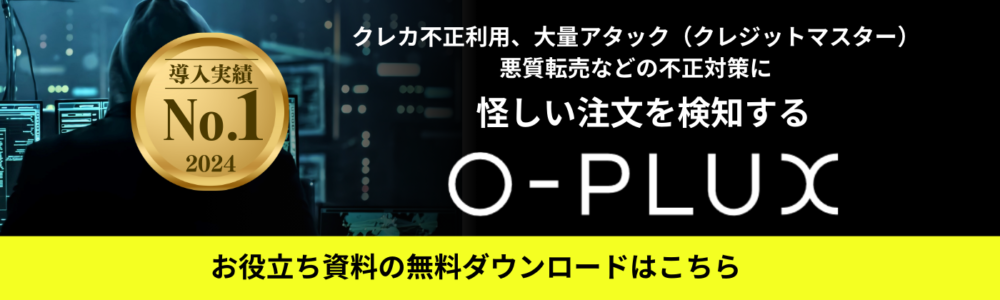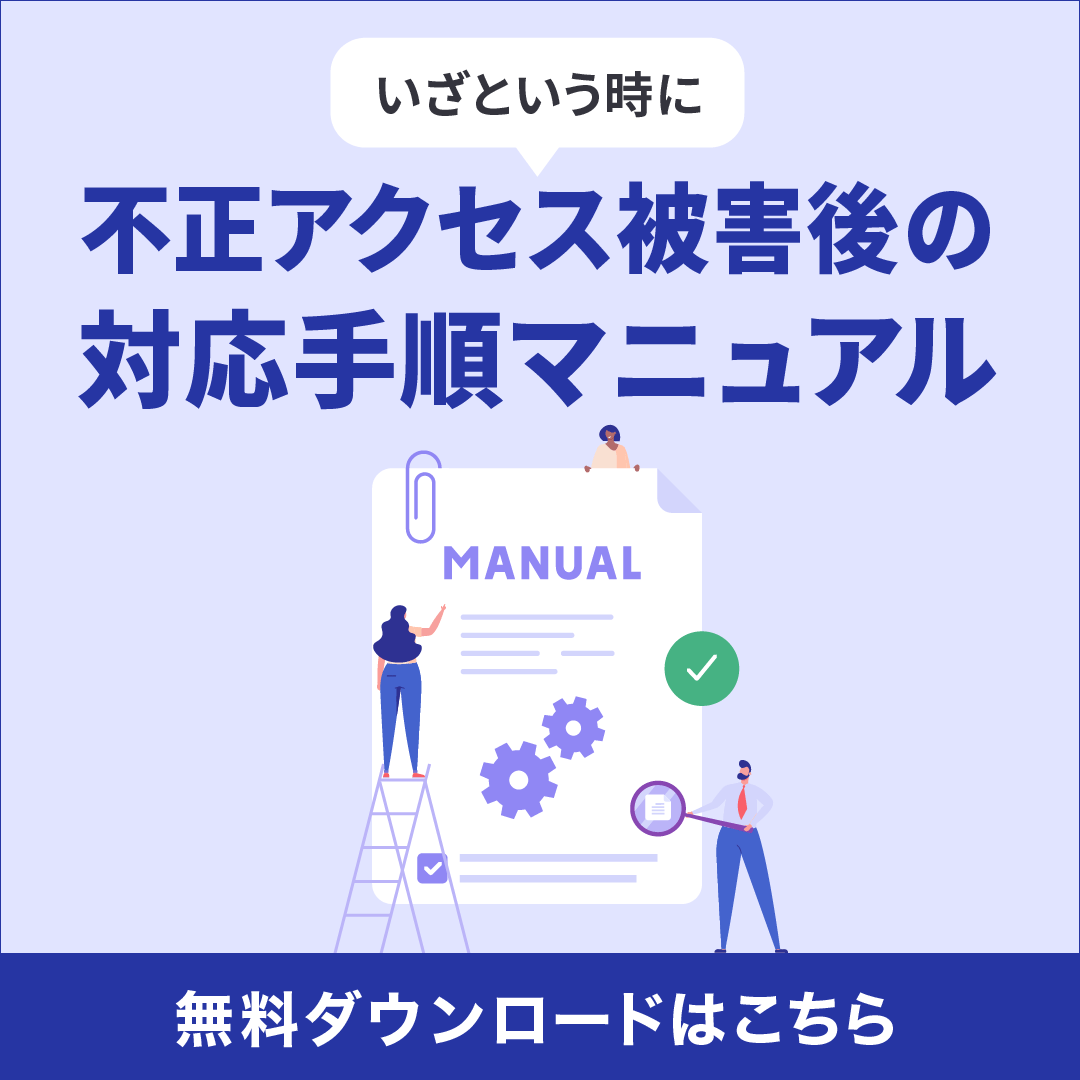商品の受取拒否は、EC事業者にとってサイト運営で起こり得るトラブルの1つです。
せっかく商品が売れても、利益を手にできないどころか、損失を出す可能性があります。
そこで、この記事では
- 受取拒否・代金引換とは何か
- 受取拒否の対処法、リスク、防ぐ対策
について、事業者・出品者目線で解説します。
受取拒否をされて悩んでいる方は、是非読んでください。
また、ECサイトの構築・運営についてのお役立ち資料は以下のバナーからできますのでぜひ参考にしてください。
目次
ECサイトにおける受取拒否・代金引換とは?
これらは、ECサイトで商品を出品する以上、知っておくべき単語です。
これを機に、再度確認しておきましょう。
受取拒否とは
「受取拒否」とは、自宅に届いた商品が何らかの理由で受け取られず、返送されてしまうことを指します。
主には、
- 意図しない場合(家族が把握していない、突然の出来事で家を不在等)
- 身に覚えのない場合(配送ミス等)
- 悪意のある場合(いたずら注文、一方的なキャンセル)
の3つに分類できます。
「受取拒否」に関する詳しい内容は、以下のページに記載しているので、是非ご覧ください。
代金引換とは
「代金引換」とは、商品代金に加えて運賃・手数料なども含めた全金額を荷物の受け取り時に支払う方法のことです。
一般に、「代引き」という名称で使われます。
これは、ECサイトにおいて、クレジットカードを持たないユーザーでもネットショッピングを利用できるメリットがあります。
一方、出品者としては決済手続き前に商品を手放すことになるため、トラブルの際に様々なコストを負担せざるを得ないデメリットがあります。
受取拒否は後払いやクレジットカード決済などでも発生しますが、中でも代金引換における受取拒否(代引受取拒否)は多発しています。
受取拒否時の対処法
受取拒否が発覚したら、順を追って適切な処置をとりましょう。
- 出品者側のミスがないか確認
- すぐに購入者へ連絡を取る
- 規定通りの対応を行う
それぞれについて、具体的に見ていきます。
出品者側のミスがないか確認
万が一、こちらが送り先を間違えているといったミスがないか、よく確認しましょう。
ミスがあった場合は、当たり前ですが返送時の送料を出品者側が負担します。
すぐに購入者へ連絡を取る
ミスがない場合には、受取拒否理由の確認や送料など諸経費の負担が最終的にどちらなのか、ここで明確にしておく必要があります。
この場合は、購入者側に送料負担してもらえることが多いです。
規定通りの対応を行う
購入者と連絡を取り、必要事項の確認ができたら、事業者側の規定に従った対応を行います。
もし購入者に説明していた内容と対応が異なると、今後のクレームやトラブルに発展する恐れが出てきます。
ひとつひとつ丁寧なやり取りを心掛けましょう。
ECサイトにおける受取拒否のリスク
どんな理由であったとしても、受取拒否が発生した場合、
- 商品自体、梱包材
- 返送にかかる送料
- 請求手続きに関する人件費や手間
- 廃棄処分
といった膨大なコスト負担が発生します。
利用規約を定めておき、購入者に費用を請求することもできますが、支払ってもらえるとも限りません。
どちらにせよ、請求手続きに必要な人件費や手間は負担しなくてはならないため、比較すると割に合わないことが多いものです。
さらに、食品や期間限定品など再販が難しい商品の場合、廃棄処分等が必要となり損害は増加します。
中には、最初から自分の利益のために代引決済を悪用する輩が増えているので、注意しましょう。
例えば、このようなケースがあります。
期間限定商品などを代引で注文しておき、並行してオークションサイトやCtoCサイトで利益を載せて出品・販売します。
そして、商品が売れた場合は代金を支払い、そのまま転売。
売れなかった場合は受取拒否をして、リスクなく利ざやを稼ごうとする手口です。
この場合、取引が通常通り完了することもあるために事業者側で不正者という判断がしづらく、何回も同じ購入者に受取拒否をされることがあります。
受取拒否を防ぐ5つの対策
受取拒否を防ぐ対策は主に以下の5つです。
- 発送前に電話やメールで連絡する
- ECサイトに注意事項を明記する
- 悪質ユーザーの顧客情報を残す
- 法的措置を検討する
- 不正対策注文に特化したサービス
加えて、代金引換における受取拒否の対策として、
- ゆうパックを利用する
- 代金引換をやめ、他の決済手段を充実させる
の2点が挙げられます。
これまで見てきたように、受取拒否の多発における事業者・出品者の損失やリスクは計り知れません。
我々は受取拒否を0にできるよう、前もって対策しておくことが求められるのです。
では、1つずつ解説していきます。
発送前に電話やメールで連絡する
近年では当たり前の連絡手段である電話やメールを用いて、「どんな内容の商品がいつ届くのか」一報入れましょう。
そうすることで、相互に内容確認ができると共に、発送してからのミスマッチを防ぎます。
ECサイトに注意事項を明記する
注意事項が明記されているショッピングは、購入者が注意事項に同意して利用していることを意味します。
これは、気軽な気持ちで受取拒否することへの抑止効果にもつながり、故意か否かに関わらず迷惑行為を減らしやすくなります。
注意事項に明記する内容としては、主に以下の2つが挙げられます。
発送後のキャンセルは不可
購入者が注文を確定した段階では、キャンセル不可にはなりません。
一般に「キャンセル不可」となるのは、商品発送後に送料が発生し、配送を止めることが難しくなった時です。
「発送後のキャンセルはできません」、「キャンセル期間は注文後何日まで」といった文言をしっかり明記しておくことで、購入者にいつでもキャンセルできると思われないようにしましょう。
また、ECサイトだけでなくメール等、複数箇所に記載しておくのも良いでしょう。
受取拒否時の請求内容や対処法
長くても、「商品発送後キャンセルの場合、返送料金および代引き手数料はお客様負担となります」や「受取拒否や発送後キャンセルの場合、往復送料、代引き手数料、梱包資材料の実費を購入者に請求いたします(送料無料の場合も含む)」といった文言を必ず明記しましょう。
文言ひとつが事業者・出品者側のリスクを減らすことに繋がります。
購入者に伝わりやすい、目に留まる情報を記載するよう心掛けましょう。
悪質ユーザーの顧客情報を残す
受取拒否があった記録を顧客情報のデータベースに残しておきます。
また、受取拒否の経緯や送料負担に関するやりとり等をまとめておくと、再度同じ購入者から注文があった際に記録を確認できます。
悪質な受取拒否の場合には、注文拒否や対象のお客様をブロックするといった措置を講じることも大切です。
法的措置を検討する
あまりにも悪質な受取拒否の時は、法的措置を検討することも視野に入れましょう。
購入者と連絡が取れない・度々無視されるといった状態では、メールや電話での受取拒否による損害請求が難しいので、内容証明郵便を利用します。
それでも請求に応じてもらえない場合は、簡易裁判所で支払督促を申し立てると同時に警察に被害届を提出するという方法もあります。
しかし、内容証明郵便や支払督促の手続きには費用も時間もかかる上、事業主・出品者への精神的負担も大きいため、実際この手続きに踏み込むケースは少ないようです。
不正注文対策に特化したサービス
受取拒否が頻発したり、事業様側での受注時の確認徹底といった対応が難しい場合には、ECでの不正注文対策に特化したサービスを検討してみて下さい。
例えば、当サイトを運営するかっこ株式会社が提供する不正検知サービス「O-PLUX」も、購入者のデータを管理し、決済前に異変を察知する仕組みとなっています。
1万円で2週間のトライアル利用も受付中!
O-PLUXのトライアルはこちら
【補足】代金引換における受取拒否対策
これは代金引換を行っている事業者・出品者様向け限定にはなりますが、注意しておくべき大事な対策ばかりなので、こちらも参考にしてください。
ゆうパックを利用する
「ゆうパック」とは、自宅で簡単に運賃支払手続とあて名ラベル作成ができ、全国一律運賃で荷物を送ることができるサービスです。
これは返送時の送料がかからないので、被害を最小限にするひとつの手段として使えます。
代金引換をやめ、他の決済手段を充実させる
まずは、代金引換を用いた決済の利用率はどのくらいなのか調べてみましょう。
代金引換の利用率がそこまで高くないのであれば、思い切って代金引換をやめるというのも1つの対策になります。
数年前と比べて、代金引換以外にコンビニ決済や後払い決済などが普及しているだけでなく、今ではPay Payや楽天ペイといった電子マネーも発達しているので、便利な決済手段を充実させることも有効なのです。
また、ECサイトの構築・運営についてのお役立ち資料は以下のバナーからできますのでぜひ参考にしてください。
まとめ
今回は、受取拒否時の対処法やリスク、防止策について、事業者・出品者目線でご紹介しました。
~受取拒否を防ぐ5つの対策~
- 発送前に電話やメールで連絡する
- ECサイトに注意事項を明記する
- 悪質ユーザーの顧客情報を残す
- 法的措置を検討する
- 不正対策注文に特化したサービス
受取拒否を正しく理解した上で、未然に防いでいけるよう対策を講じていきましょう。
また、起こってしまっても、冷静な対応と再発防止を心掛けてください。
消費者庁のホームページには、「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」が記載されているので、ECサイトに注意事項を明記する際には必ず読むようにしましょう。
不安に思っている点や抜け落ちていると感じる点があれば、いつでもご相談ください。
1万円で2週間のトライアル利用も受付中!
O-PLUXのトライアルはこちら