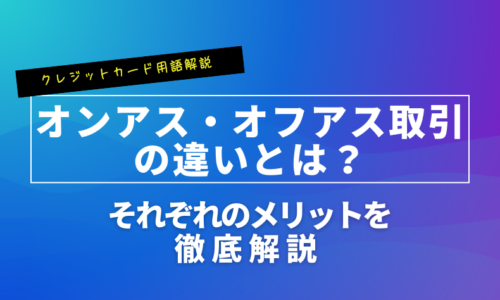「Suica、PayPayって不正利用されるの?」
「電子マネーの不正はどのように行われるのか、対処法はあるのか知りたい」
このように考えている方もいるのではないでしょうか。
電子マネーとは、SuicaやPayPayなどのスマホで決済できるお金のことです。
本記事では、以下の内容についてご紹介します。
- 電子マネーによる不正利用の現状
- 電子マネーが不正利用されるパターン
- 電子マネーが不正利用された場合の対処法
- 電子マネーの不正利用を防ぐ方法
電子マネーを利用する消費者向けの内容はもちろん、事業者向けの不正利用を防ぐ方法についてもご紹介しています。
電子マネーの不正利用を防ぐ方法について知りたい方は、ぜひご一読ください。
目次
電子マネーの不正利用が増えている
関東財務局によると、電子マネーを悪用した被害が増えています。
インターネット有料サイトの利用料金未納などを騙った架空請求やサクラサイト等、詐欺行為の支払手段として電子マネーを悪用した被害が急増しています。
※引用:関東財務局
電子マネーが不正利用されるパターンは、以下の3つがあります。
- コンビニなどで相手の電子マネーにチャージしてしまった
- クレジットカードや銀行口座から、他人の電子マネーに不正な送金が行われた
- 紛失したスマートフォンを勝手に利用され、電子マネーが不正利用される
怪しいメッセージに反応して電子マネーを送金しないのはもちろん、カードやスマートフォンを紛失しないよう注意する必要があります。
スマートフォンの場合は、パスワードロックや生体認証によるセキュリティ強化もおすすめです。
電子マネーが不正利用された場合、サービスによっては補償を受けられる可能性もあります。
不正利用された場合、補償を受けられる可能性がある
電子マネーを不正利用された場合、被害を受けた方は補償を受けられる可能性があります。
たとえばPayPayで不正利用が発生した場合、条件を満たせば補償を受ける可能性が高いです。
一方、不正利用に対する補償がない電子マネーもあります。不正利用に対する補償があるかどうかも、利用する電子マネーを選ぶ際の判断材料になりそうです。
電子マネーの加盟店はチャージバックに要注意
電子マネー決済を採用しているECサイトは、不正利用によるチャージバックの発生に注意が必要です。
【補足】
電子マネー=スマートフォンで決済できるお金のことです。モバイルSuicaやPayPayなどがあります。
チャージバックとは、クレジットカードや電子マネーを不正利用された場合に、売上が取り消されることです。
たとえば他人の電子マネーを不正利用して自社ECサイトで買い物が行われた場合、チャージバックのリスクが発生します。
チャージバックが発生すると、商品が返品される可能性は極めて低く、売上も回収できません。チャージバックの発生原因や対策について、詳しくは以下記事をご一読ください。
電子マネーを不正利用される4つのパターン
電子マネーが不正利用されるパターンは、以下の4つがあります。
- スマートフォンやカードの紛失
- スマートフォンやカードの不正利用
- なりすましによる不正利用
- QRコードのすり替えによる詐欺
各パターンについて、詳しくご紹介します。
1. スマートフォンやカードの紛失
電子マネーの不正利用を防ぐため、スマートフォンや電子マネーのカード(Suicaカードなど)を紛失しないように心がけましょう。
たとえばSuicaの場合、カードを紛失して第三者が拾うと簡単に不正利用ができてしまいます。
スマートフォンも同様に、設定次第では簡単に電子マネーが悪用されてしまいます。
スマートフォンやカードを紛失しないよう、決められた場所に必ず保管するなど、管理を徹底することが大切です。
2. スマートフォンやカードの不正利用
スマートフォンやカードの不正利用によって、電子マネーの悪用リスクがあります。たとえば、以下のようなケースが考えられます。
- 紛失したスマートフォンを第三者に使用されて電子マネーを不正利用される
- 流出したクレジットカード情報が悪用されて電子マネーで不正利用される
スマートフォンのセキュリティ設定を行ったり、不正利用が疑われる場合はサービスの利用を止めたりして悪用を防ぎましょう。
3. なりすましによる不正利用
なりすましによる電子マネーの不正利用も考えられます。なりすましの例としては、主に以下の3パターンが考えられます。
- 第三者のスマホを不正に入手して、電子マネーを悪用
- 第三者のクレジットカード情報を不正入手して、電子マネーに変えて悪用
- キャリア決済のIDとパスワードが流出し、第三者が不正アクセスを行い悪用
スマホを盗んで不正利用するだけでなく、流出した情報が悪用されるパターンもあります。正利用が疑われる場合は、すぐにサービスの利用停止を申請しましょう。
4. QRコードのすり替えによる詐欺
QRコードをすり替えて売上を盗む不正が発生しています。
たとえば小売店のレジにあるQRコードのうえに、悪意ある第三者によって別のQRコードが貼り付けられます。たったこれだけで、お店の売り上げが横取りされてしまうのです。
QRコードがすり替えられているかどうかは、一見しただけは判別しにくいです。不正を防ぐため、QRコードは決済を行うとき以外は隠しておくことをおすすめします。
次は、電子マネーが不正利用された場合の対処法についてご紹介します。
電子マネーを不正利用された場合の対処法
電子マネーの不正利用に気付いたら、チャットサポートや電話窓口に連絡し、すぐに利用停止の手続きを行いましょう。
会社からの補償を受けるには、警察への届出が必要なので、サービスの利用停止手続きが終わったら届出を行いましょう。
被害届が受理されると受理番号が貰えるため、電子マネーの運営会社やカード会社に連絡して共有を行います。
不正利用かどうかの判断が難しい場合でも、警察への相談をおすすめします。
【加盟店向け】電子マネーの不正利用を防ぐ3つの方法
飲食店やEC事業者も、電子マネーの不正利用を防ぐための対策が必要です。
不正利用への対策を怠ると、電子マネー決済での売上が回収できなかったりチャージバックのリスクが発生したりします。
加盟店が行える電子マネーの不正利用への対策は、以下の3つがあります。
- 安全性の高い電子マネー決済システムを利用する
- 普段はQRコードを隠しておく
- 不正注文検知システムを利用する
どういうことか、詳しく見てみましょう。
【方法1】安全性の高い電子マネー決済システムを利用する
電子マネー決済を導入する際は、セキュリティがしっかりしているか確認することが大切です。
決済システムのセキュリティは、運営会社によって安全性が異なります。複数社の電子マネーを比較して、どのサービスがセキュリティ面で問題なさそうか、比較検討をおすすめします。
【方法2】普段はQRコードを隠しておく
飲食店や小売店でQRコード決済を導入しているのであれば、普段はQRコードを隠しておくのがおすすめです。
レジにあるQRコードのうえから別のQRコードが貼られてしまい、店の売り上げを奪われる事例が発生しています。
コード決済の売上を盗まれないためにも、普段はQRコードを隠しておきましょう。
【方法3】不正検知サービスを利用する
電子マネーの不正利用を防ぐため、EC事業者は不正検知サービス導入をおすすめします。
本記事前述の「1.2 電子マネーの加盟店はチャージバックに要注意」でも書いている通り、電子マネーを使った不正な注文が入ってしまうと、チャージバックの発生リスクがあります。
不正な注文を目視でチェックするのは大変なものなので、不正注文を検知するシステムの導入がおすすめです。
たとえば、不正検知サービス「O-PLUX」では注文情報をリアルタイム審査を実施しており、商品を発送する前に不正注文を見抜くことができ、チャージバックの発生も防ぐこと可能です。
O-PLUXを導入しているサイト数は累計120,000を越えており、それらのサイトで発生した不正注文のデータベースを参考にしているため不正検出の精度が高く、多くの方から好評を頂いています。

\導入企業様のインタビューを公開中!/
導入事例一覧はこちら
O-PLUXで検知した不正な情報は全サイトで共有しており、高い精度での不正検知を実現しています。
不正検知サービス「O-PLUX」について詳しく知りたい方は、以下をご確認ください。
1万円で2週間のトライアル利用も受付中!
O-PLUXのトライアルはこちら
【消費者向け】電子マネーの不正利用を防ぐ2つの方法
事業者だけでなく一般消費者も、電子マネーの悪用対策を行うことが大切です。電子マネーの不正利用を防ぐ方法は、以下の2つがあります。
- スマートフォンのセキュリティ設定を行う
- ID・パスワードの使い回しを避ける
各方法について、詳しくご紹介します。
【方法1】スマートフォンのセキュリティ設定を行う
電子マネーの不正利用を防ぐため、事前にスマホのセキュリティ設定を行いましょう。主なスマホのセキュリティには、以下の3つがあります。
- パスワードロックを設定する
- 生体認証を設定する
- 遠隔でロックできるよう設定する
パスワードロックを設定すれば、万が一スマホを紛失してもアプリの操作ができないため、不正利用されにくいです。生体認証に対応したスマホをお持ちの場合は、指紋認証や顔認証の活用をおすすめします。決済時に生体認証を要求されるため、不正利用されにくくなります。
不正利用を防ぐため、遠隔でスマホをロックできるようにするのもおすすめです。iPhoneの場合は「探す」アプリ、Androidの場合は「デバイスを探す」アプリを活用することで、遠隔でスマホをロックできます。
【方法2】ID・パスワードの使い回しを避ける
IDとパスワードを使い回さないことも、電子マネーの不正利用対策としておすすめです。
IDとパスワードが流出した場合、第三者が流出した情報を悪用して、他のサイトでログインを試みることがあります。同じIDとパスワードを使い回していると、複数のサイトで不正アクセスされるリスクが高くなります。
IDとパスワードは使い回さないようにしましょう。「設定したIDを忘れてしまう」という方は、パスワード管理アプリやメモ帳に記録するなど、管理方法の見直しをおすすめします。
まとめ
本記事では、電子マネーの不正利用についてご紹介しました。
電子マネーはスマホの紛失や、なりすましによって勝手に利用されてしまう危険性があります。
電子マネーを不正利用されると、EC事業者にはチャージバック発生の恐れがあります。
消費者・事業者の双方にとって、電子マネーを不正利用されないための対策は、
- 消費者:スマートフォンのセキュリティ設定を行ったりパスワードを使い回したりしない
- EC事業者:電子マネーやクレジットカードの不正利用対策を行う
不正利用が発生すると、EC事業者にはチャージバックのリスクが発生します。
しかし「不正利用の対策といっても、何からはじめるべきか分からない」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
そこでEC事業者向けに、不正対策についてまとめた無料のお役立ち資料をご用意しました。
不正利用の対策について詳しく知りたい方は、ぜひ無料でダウンロードしてチェックしてください。
1万円で2週間のトライアル利用も受付中!
O-PLUXのトライアルはこちら



-8-1000x300.png)