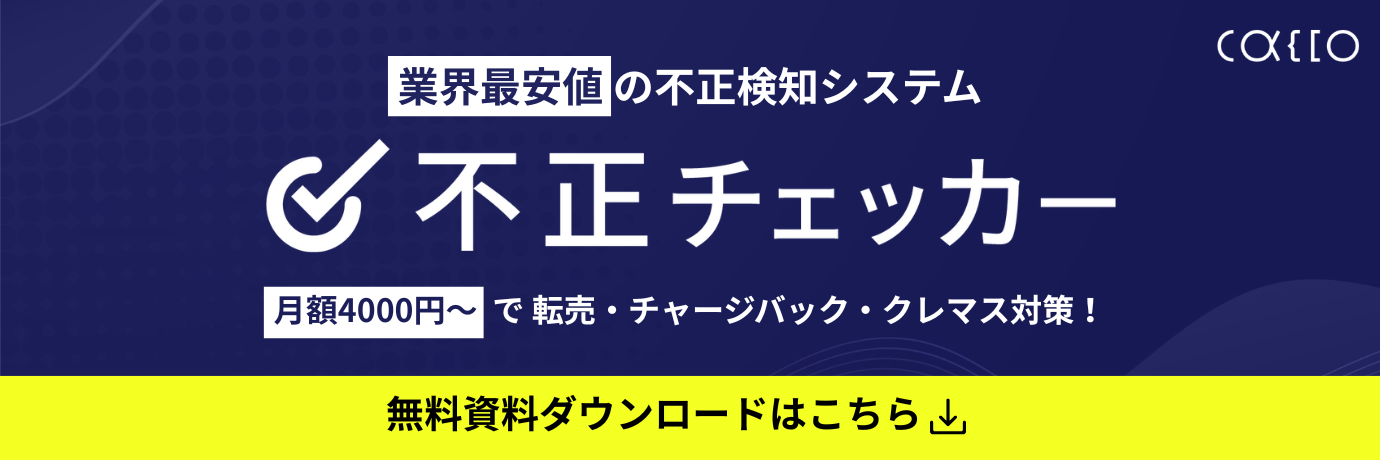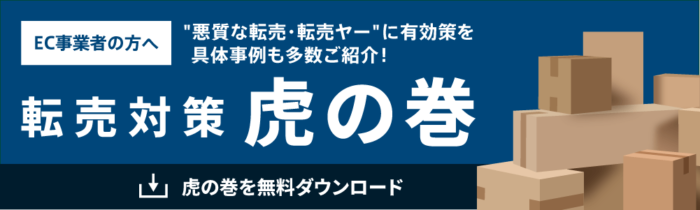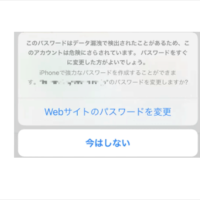事業者の方々は、ネット通販等でおこっている悪質な転売に悩まされていないでしょうか。
特にターゲットになりやすい、アーティストのチケットや高額ブランド商品の不正転売は、近年メディアでも取り上げられるようになり耳にする方も多いと思います。
記憶に新しいところでは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、マスクや消毒剤など必需品の買占め・転売が指摘されました。
そこで、この記事では
- 転売の現状
- 不正転売を防ぐための対策
- 業界別に見る転売事例
について解説します。
\転売・チャージバック対策を業界最安値で/
不正チェッカーの資料DLはこちら
目次
転売の現状
皆さんは、「転売」という言葉の意味をしっかり理解できているでしょうか。
この章では、転売について以下のとおり解説します。
- 転売とは?
- 転売が企業にもたらす影響
- ブランドイメージの低下
- サービスのパフォーマンスの低下
転売とは?
転売とは、購入品に改めて値段をつけ、他の人に販売する行為です。
例えば、誤って同じ商品を2つ買ってしまった、あるいは自分で使う予定で購入した商品をCtoCサイトで誰かに販売する行為も「転売」です。
つまり、自社以外で作成した商品を求めている人に売り渡す行為なので、転売そのものに違法性はありません。
メルカリやラクマといったフリマサイトで売ることも転売の1つと言えます。
※但し、コンサート等のチケットは「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」の対象となり、違法になる場合もあります。
現在問題視されている転売は、不当に価格を釣り上げたり、生産者が禁止しているにも関わらず取引を行う悪質な転売。
つまり、「不正転売」と表現されるものです。
また、チケット関連の不正転売に関しては、以下の記事で詳しくまとめています。
転売が企業にもたらす影響
上記にも述べたように、転売自体は悪いことではありません。
しかし、いつ身近で起こるかわからない転売がどんな問題点を抱えているのか、きちんと把握しておきましょう。
ブランドイメージの低下
これは、自社の商品がフリマサイト等で転売されると、商品自体だけでなくその商品のブランドイメージが低下することを指しています。
転売先で商品が低価格販売されることは、正規ブランドでの購入者減少を引き起こしかねません。
逆に、高価格で商品が販売された場合はどうでしょうか。
転売者が買い占めることで、商品が本来行き渡るはずの人々の元へ届けることができないという問題が起こります。
商品を取り扱う運営者・生産者だけでなく、正規の手段で取引しようとしていた購入者の利益が損なわれるのです。
サービスのパフォーマンスの低下
仮に、はじめのうちは商品を転売者が買い占めても、企業の売れ行きは良好でしょう。
ですが、サービスが利用されていく上で、消費者からの声は評判や拡散力として絶大な影響力を持っています。
実際に利用してくれる人々のいないサービスは、利益の低迷につながるのです。
転売の手口は年々組織化・巧妙化している
以前は、個人がネット通販の商材を初回特別価格で購入し、フリマサイトなどで通常価格よりも安い価格で売りさばき、お小遣い稼ぎをする程度でした。
しかし、転売の手口は年々組織化・巧妙化しており、企業が被る被害も拡大しています。
中には大勢のアルバイトを雇い、転売マニュアルに沿って商品の購入と転売を繰り返し行う悪質な転売屋もいます。
また、こうした転売屋は以下のような手順で転売を行なっているケースもあります。
- 手元に商品がない状態でフリマサイトに出品
- 商品が購入される
- 購入者の個人情報を使って商品を申込む
- 商品が購入者のもとに届く
- 定期購入を解約
このような転売を防ぐためには、企業側の対策が必須です。具体的な対策方法については次の章で説明します。
不正転売から企業を守る11個の対策
不正転売から企業を守る対策は主に以下の11個です。
- 通常価格と差の小さい価格設定にする
- 定期コースの割引率を固定する
- 初回購入の前にモニター商品を購入してもらう
- 申込フォームの前にチェックボックスを設ける
- 申込の確認画面に転売対策の文言を追加する
- 複数回の初回購入を把握する
- 後払い決済を利用する
- Googleアナリティクスを確認する
- 企業間連携による協力をする
- 販売時に商品の価値を下げる
- 不正検知サービスの導入
これまで見てきたように、不正転売の多発は企業の損失やリスクが計り知れません。
現在の不正転売に対する規制は十分でない為、転売によって誰もが不利益を被ることがないように、各企業は自分たちで対策を講じることが必要不可欠です。
では、1つずつ解説していきます。
通常価格と差の小さい価格設定にする
転売で利益を得るためには、転売の必要経費(出品手数料や配送料)を引いた上で儲けが出る状況にしなければなりません。
その為、通常と差の大きい価格設定(初回やイベントにおける割引)の商品は、転売屋のターゲットになりやすいです。
儲けがほとんど見込めない、すなわち転売で利益を生み出させない価格差の目安は1,000円前後がおすすめです。
定期コースの割引率を固定する
初回価格と2回目以降の価格を同じにし、「初回も2回目以降もずっと15%オフ」というように定期コースの割引率を固定するのも効果的です。
転売屋は、初回特別価格で安く仕入れ利益を得ているため、定期コースの割引率が一定だと利益を出せなくなります。
また、この方法であれば、本気度の高い顧客のみを集めることができるため、LTVを向上させることも可能です。
LTVとはLife Time Valueの略で、顧客から生涯にわたって得られる利益のこと。日本語では顧客生涯価値と訳される。
初回購入の前にモニター商品を購入してもらう
初回購入の前にモニター商品を購入してもらうことも転売対策になります。
転売の被害を受けている企業は、検索結果や広告などを経由して訪問者が最初にアクセスする「ランディングページ」にいきなり初回特別価格を記載してしまっているケースが多いです。
そこで、初回購入の前に無料もしくは低価格のモニター商品を購入してもらい、
- モニター商品の申込確認画面
- モニター申込者に送るメールやモニター申込者限定のランディングページ
などにのみ初回特別価格を記載すると良いです。
申込フォームの前にチェックボックスを設ける
申込フォームの前に回答必須のチェックボックスを設けるのも一つの手です。
チェックボックスは以下のようなものを設置すると良いでしょう。

また、チェックボックスを設けると、本商品の申込をする可能性が高いモニターを集めることができるので、売上アップを期待できます。
申込の確認画面に転売対策の文言を追加する
申込の確認画面に転売対策の文言を追加することで、転売の抑止力になります。
転売対策の文言の例としては以下のようなものが挙げられます。
- 転売目的の申込が発覚した場合には警察に届け出ます
- ポイント目的で申込をし即解約した場合にはポイントを無効とします
このような文言を記載しておくと、転売やポイント目的の購入がしづらくなり、不正注文の削減につながります。
複数回の初回購入を把握する
大半の通販会社は、初回価格の購入回数を1回に設定しています。
しかし、転売屋は商品を安く仕入れるため、住所のパターン化や捨てアカのメールアドレスを複数回利用するといった様々な方法で、会員情報を偽って別のユーザーになりすまします。
ノジマでは、ID紐づけの限定販売を行うことで、複数回の初回購入を防止しようとしています。
不審なユーザーをいち早く見つけるために、目視での確認や情報を溜めていくといった地道な作業は、転売対策に欠かせません。
後払い決済を利用する
これは、購入者の手元に商品が到着後、コンビニや銀行で料金を支払う決済方法の1つです。
利用されている例としては、Amazon, 楽天, PayPayなどが挙げられます。
近年では、クレジットカードを所持していない、あるいはクレジットカード情報流出の恐れがないために使用する人も増加しています。
- 蓄積した情報を用いて、購入者が悪質であるか判断する
- 後払い可能なユーザーか見極め、最初から省く
- 発信不可能な電話番号登録ユーザーも事前に発送リストから除外する
以上のように事業者側の後払い決済メリットも多くあります。
ただし、独自に後払い決済を利用することは時間と手間がかかるため、必ずしも得策であるとはいえません。
かっこ株式会社では、EC・通販事業者のために後払い機能を一つにまとめたパッケージを提供しておりますので、ご興味がある方は是非以下のページをご覧ください。
\ 後払いの仕組みを簡単構築/与信・入金管理・請求督促の自動化機能をパッケージ化 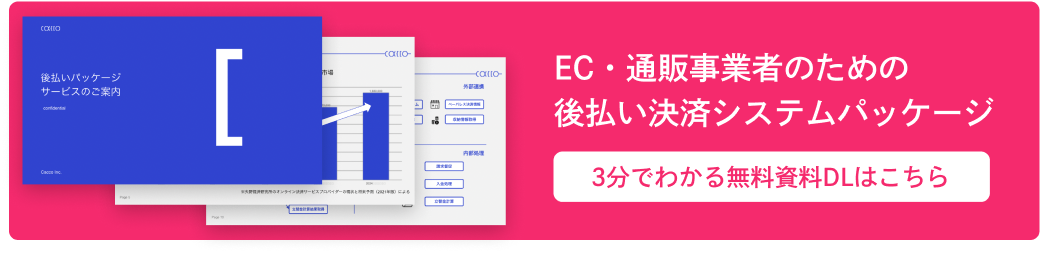
また、かっこの公式サイトでは、転売対策として「O-PLUX」を導入した事例インタビューが掲載されています。
不正検知サービスを用いた不正対策を検討している方は、一度目を通してみてください。
- 株式会社AIJ:転売対策
『後払い決済の督促対応にかかる時間がわずか30分に!共有ネガティブの効果を実感』
- 大網株式会社:チャージバック対策
『常に時代を先取りし、ホビー・フィギュア越境ECでも先駆けとなった大網が、初めて遭遇した不正注文被害にとった対策とは?』
(補足)広告を出す際の不正転売対策
これは広告を打っている事業様向け限定にはなりますが、注意しておくべき大事な対策ばかりなので、こちらも参考にしてください。
広告のパラメータを利用する
広告を運用する際、どのパラメーターがついたURLから購入があったのか分かる設定にすることが大切です。
転売界隈では購入URLが共有されているため、転売ターゲットの対象商品は特定のURLから購入数が一気に上がることがあります。
代理店や媒体ごとにURLのパラメーターを分類しておくことで、購入数が異常な場合にどのURLからの購入であるか知ることができます。そして、特定の広告のみを止めることが可能です。
アフィリエイト広告配信の提携種類
アフィリエイトとは、インターネットを利用した広告プログラムの一種です。
提携の種類は、主に以下の3つがあります。
- 自動承認(誰でも掲載可能)
- 手動承認(依頼主の承認が必要)
- クローズド(アフィリエイトサービス会社の人が有力な人にのみ紹介)
自動承認は、手間があまりかからない一方、フィルターを通さないため危険も伴います。
転売屋がアフィリエイターとなり、「転売での利益」と「アフィリエイト経由での成果報酬売上」の2つを収入源としていることがあるのです。
アフィリエイト広告では、手動承認あるいはクローズドを利用することをオススメします。
【参考】業界別にみる転売の事例
転売の標的は、人気アーティストのチケットや高額なブランド品、初回購入の割引対象商品など様々です。
ここでは、業界別に転売の標的にされやすい商品と現状をまとめました。
| 業界 | 転売の標的にされやすい商品と現状 |
| 家電 | PC、タブレット、美容家電、カメラなどを狙った高額転売 |
| MVNO (格安SIM提供事業など) | 買い増しサービスや会員限定価格が設定されている割引商品などを狙った転売 |
| 健康食品・サプリ | 初回購入割引が設定されている商品などを狙った転売 |
| コスメ | 季節限定コスメ、限定モデル、話題になり需要過多の商品などを狙った高額転売 |
| ブランドアパレル | 限定モデルや生産数が限られている商品、福袋などを狙った高額転売 |
| チケット | トレンドになっているアーティストやタレントのライブや舞台を狙った高額転売 |
不正転売は、あなたの身の回りにありふれています。
商品購入の際には、
- 売り手が誰であるか明確(怪しい事業主でないか)
- 安すぎる価格設定ではないか
といった個人でも注意できる小さなことから気を付けていきましょう。
まとめ
今回は、転売とはどんなものであるかや不正転売防止対策、押さえるべき転売事例についてご紹介しました。
インターネットが発達し便利な時代になりましたが、それと共に悪巧みする人が一定数いることも事実です。
消費者が節度を持って気持ちの良い買い物ができるよう、企業はできるだけ不正転売を未然に防いだり抑制する必要があります。
~不正転売から企業を守る11個の対策~
- 通常価格と差の小さい価格設定にする
- 定期コースの割引率を固定する
- 初回購入の前にモニター商品を購入してもらう
- 申込フォームの前にチェックボックスを設ける
- 申込の確認画面に転売対策の文言を追加する
- 複数回の初回購入を把握する
- 後払い決済を利用する
- Googleアナリティクスを確認する
- 企業間連携による協力をする
- 販売時に商品の価値を下げる
- 不正検知サービスの導入
これを機会に、自社で行われている不正転売対策を振り返ってみてください。
不安に思っている点や抜け落ちていると感じる点があれば、いつでもご相談ください。
\6社の転売対策事例を載せた「虎の巻」が完成しました!/
転売対策「虎の巻」DLはこちら